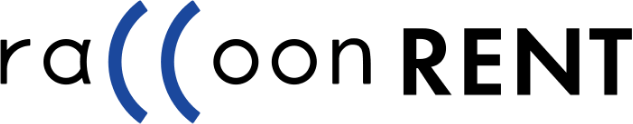住宅ローン特約にもとづく解約期日の解説 実際の裁判事例での判決も紹介

住宅ローン特約にもとづく解約期限の延長は口頭でも可能か?不動産売買においてよく見られるこの問題について、裁判例をまじえながら詳細に検討します。書面が常識とされる大きな取引で、口頭だけの合意が法的に有効なのか。このケースがどう裁定されたのか、注意点とともに解説します。
※この記事は2022/10/11にラクーンレントメルマガで配信したものを加筆修正したものです。
さて、今回は、賃貸ではなく売買に関する事例について取り上げます。その中でも、皆様が特に気をつけていらっしゃる決済まわりに関するトラブル事例にフォーカスします。
具体的には、住宅ローン特約にもとづく解約期日(期限)は、口頭でも延長できるのかという点について検討したいと思います。一般的に、売買契約書中において「住宅ローンが通らなかった場合は、〇月〇日までに解約すれば、手付金もちゃんと返還される形で解約できますよ」という条項が大抵あるでしょう。
その「〇月〇日」という解約リミットを、口頭で変更(延長)できるのかという問題です。このような延長合意をする場合、大半のケースではきちんと「念書」のような形で書面にされていると思います。
中には、何らかの事情で、口頭での約束を先に済ませておいてあとから書面に残す、といった運用がなされるケースがあるでしょう。
こういう場合において、延長期限経過後に、やっぱりローンが通らなかったと言って解約になると、延長合意があったのか無かったのかと問題になります。
住宅ローン特約にもとづく解約期日の法的扱いは
結論として、口頭でも延長の合意はできます。まず、法律の原則として、契約、つまり合意というのは、口頭でも成立するが原則です。
「住宅ローンが通らなかった場合は、〇月〇日までに解約すれば、手付金もちゃんと返還される形で解約できますよ」という条項は、契約のイチ内容であり、その期日を変更する「合意」は、基本的に口頭でも成立するのです。契約書は、あくまでのこの口頭での合意を確実に残すための書面です。
つまり、本来口頭でも成立する契約を、その存否で揉めないように、書面に残したものが契約書です。そして、不動産売買という大きな取引については、なお慎重に取り扱う必要がある為、大抵の場合で、「契約書」「念書」のような形で書面にするのです。
とはいえ、不動産売買のような大きな取引では、契約書なり書面に残すのが通常(常識)と言えますので、口頭のみで合意が成立していた事が認められるにはそれなりのハードルがあります。
少額の金銭の貸し借りなどは、口頭で話しただけで借用書は作っていないというケースが、社会通念に照らして容易に想定できますね。
しかし、住宅の購入という場面で、そのような気軽な(ラフな)約束、合意というのは、常識的に考えてなかなか無いだろうという前提があるのです。そのため、「(例外的に)口頭のみで延長の合意があっただろう」という事を強く推測させるような事実が必要になってくるのです。
例えば、以下の裁判例にあるような事実が必要になってきます。
実際の裁判事例をもとに解説
ここで1つ裁判例を紹介します。“東京地裁令和3年1月6日判決”で、ローン特約にもとづく解除期限の延長について、口頭での合意があったことを認めた裁判例です。
よくある土地売買の事案なのですが、この事案では、解除期日を延長したことを証する書面の類はありませんでした。
ですが、以下①②のような事実があったため、裁判所としては、口頭で延長の合意があった旨を認定しました。
以下①②の事実が、口頭での延長合意の存在を強く推測させたということになります。なお、買主が最初に事前審査の申込をした金融機関からの回答は、1000万円の減額回答でした。
① 買主が融資先の金融機関を確保できていない状況下で、住宅ローン特約に基づく解除の期限が切れる1日前に、3者(売主、買主、仲介)で面談をした。
その面談の中で、原告の融資の見通しがつかない旨及び住宅ローン特約に関する話がなされた事実、
② 期限経過3日後に作成された「確認書面」という売主買主間で作成された書面中において、現在買主の都合で融資金融機関を選択中である旨が記載されているものの、ローン特約に関する記載はなかった事実①の事実に関し、被告(売主)側としては、上記面談時に、買主が、ローン特約の延長はせず、売買契約自体は予定通り維持する(決済日はそのまま)と述べていた旨を主張しました。
しかし、融資の見通しがない状況で、買主として、ローン特約の期日は延長せずに、決済日だけ維持する旨の主張をすることは、買主が単にローン特約による解除権を放棄するに等しい、つまり手付金を失って解除による違約金請求を受けるリスクを一方的に受ける主張であり、不自然な主張であるから、買主がそのような主張をしたことは考えにくいと裁判所は認定しました。
②の事実については、延長合意をしたなら、その旨も書面に書くはずだということです。
いかがでしょうか。個人的には、1000万程度の減額回答がなされている状況であれば、買主として、「不足分は自己資金で補うことができるけども、一応他行も出してみる、期日は従前通りで問題ない」という主張を行うことも十分想定できるかと思いますので、上記の主張が一律不自然とは思いません。
しかし、裁判所がこのような認定をしていることは頭に留めておいても宜しいかも知れません。
また、本件はいわゆる、両手型の事案であり、仲介業者は、証人として、口頭での延長合意があった旨を供述しており、その信用性が高かったという事情もあります。
片手型の事案で、元付と客付の供述が真っ向から対立した場合などは、また変わってくるかも知れません。
類似の事例だと、例えば、ローン特約の期限直前に、売主や元付業者から、買主に対して、新たな金融機関を紹介した、等の事例でしょうか。
延長がなければ、直前に新たな融資先を紹介しないと裁判所が考えることは十分想定できますので、このような事実があった時に、口頭での延長合意があったことを推測すると言えるかと思います。
以上、今回は売買におけるローン特約の延長合意について取り上げました。
少しでも皆様の事業のお役に立てれば幸いです。
編集部追記:住宅ローン特約とはそもそもなにか
不動産売買において、「住宅ローン特約」とは、購入者(買主)が住宅ローンを組むことが前提となる取引において、特定の条件下で契約を解約できるようにするための特別な条項のことです。具体的には、この特約は「住宅ローンが承認されなかった場合、売買契約を解約できる」といった内容を含むことが多いです。
「解約期限の延長」とは、もともと契約に設定されていた解約が可能な期日(期限)を後にずらすことを指します。例えば、契約書で「住宅ローンが〇月〇日までに承認されなかった場合は解約可能」とされている場合、何らかの事情で住宅ローンがその期日までに確定しない可能性が出てきた時に、売主と買主が新たに合意をしてその「〇月〇日」という期日を延長することが考えられます。
この解約期限の延長が口頭で行われた場合、その合意が法的に有効かどうかが問題となるケースがあります。合意が成立しているかどうかが不明確な場合、解約が行われた後にその合意が問題とされ、争いが起きる可能性があります。だからこそ、書面での確認が重要とされるのです。